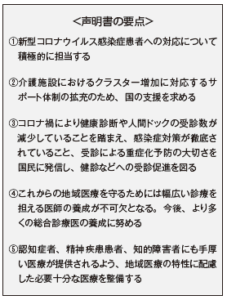福祉車両の扱い学ぶ講習会 座学・実技で解説 福祉車両安全研究会
2021年3月17日
カーリースのアイ・ティ・エスが立ち上げた非営利団体福祉車両安全研究会(東京都杉並区)では、施設管理者、送迎ドライバー向けの事故防止講習会を昨年12月より実施している。施設を個別に訪問し、座学と実車を用 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード