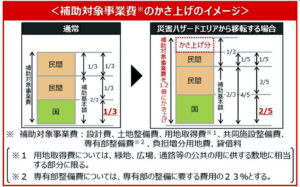国交省に政策提言「入居相談窓口の設置や相談員育成を」 一般社団法人高齢者住宅協会
2021年12月17日
一般社団法人高齢者住宅協会(東京都千代田区/以下・高住協)は10月4日、国土交通省に「最期まで自分らしい生活を送ることができる住生活の実現を目指して~大量供給からの転換~」とした政策提言をした。高齢者 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。