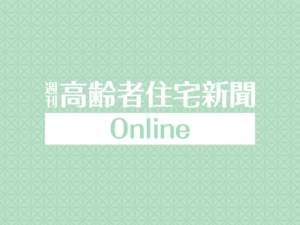サ高住入居者にケア制限 厚労省が「囲い込み」防止策/浅川澄一氏
2022年2月4日
2011年10月に施行された「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」が10年を迎えた。 国交省は普及させようと、1部屋当たり100万円もの破格の高額補助金を投入してきた。人気が高ま ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード