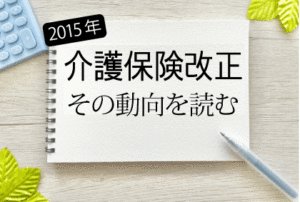和太鼓演奏で介護予防 バチを使ったストレッチも 音健アワード入賞作品
2022年2月19日
前号(1月19日号)で紹介した「一般社団法人日本音楽健康協会(東京都品川区)」が主催する、優れた音楽レクリエーション事例を表彰する「音健アワード2021」。入賞した10作品の中には、高齢者施設での音楽 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード