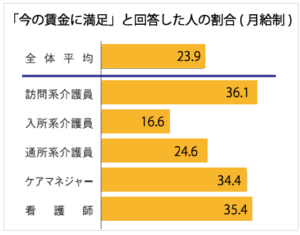給与制度を刷新 社会福祉法人若竹大寿会
2022年3月7日
社会福祉法人若竹大寿会(横浜市)は昨年12月、給与水準の引き上げを目的に、給与制度を大幅に見直し、能力給制度を導入した。 求められる役割と成果に応じて10階級にグレード分けし、上位に移行すると年収が増 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード