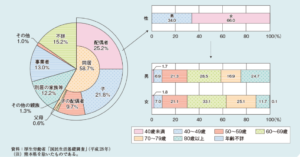超強化型老健「在宅復帰率」と「稼働率」両立 訪室回数適正に 社会福祉法人ほたか会
2022年12月23日
社会福祉法人ほたか会(群馬県前橋市)が運営する介護老人保健施設「青梨子荘」(同)は、100床の超強化型。重度の人や認知症の人などほかの施設で〝受け入れ困難な〟人も幅広く受け入れ、リハビリに注力する。在 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード