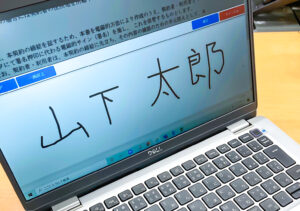東京都大田区、福祉人材の連携推進 人材育成・交流センター新設
2022年12月21日
東京都大田区では今年4月、区内の福祉人材確保とスキルアップを目的に、福祉管理課内に大田区福祉人材育成・交流センターを設置。研修の実施などに加えて、事業所やサービス種別、支援分野を超えた「横のつながり」 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード