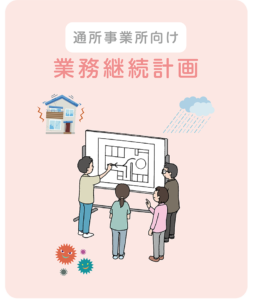【特別インタビュー】建築家 隈研吾氏 介護施設建築の哲学
2023年4月21日
木材などその土地の素材を豊富に使用し、周囲と調和した建築を流儀とする建築家、隈研吾氏。携わった作品として国立競技場などが有名だが、介護施設も複数手掛けてきた。今回は昨年6月に新設された、特別養護老人ホ ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード