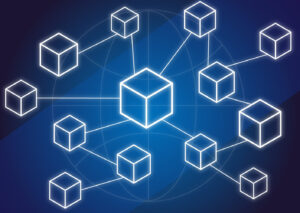苦労の先に得られる成果 ICT人材の育成(後半)【つなぐ支えるICT】
2023年5月13日
山梨県立大学人間福祉学部・福祉コミュニティ学科の伊藤健次准教授は大学での教育と並行し、厚生労働省「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」の構成員などの活動も行ってきた。後半では介護現場へのテクノロジー ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。