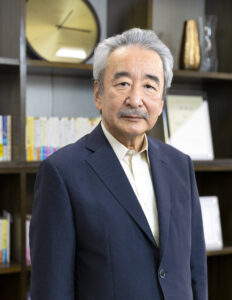「ケアをマネジメントする」とは何か/みさと中央クリニック 髙橋 公一氏
2023年5月18日
その人を子細に知り尽くす生活の大部分を占める「食事」「排泄」「入浴」という活動をサポートするためにケアがあるとするならば、それをマネジメントすることを生業として ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。