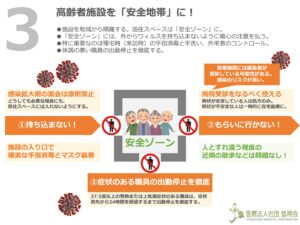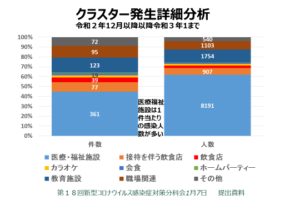≪コロナ政策 中間評価と緊急提言≫ 第1部 課題と分析 Ⅱ.2つの評価
2020年12月26日
---連載② ニューヨークの死亡者、東京の100倍---Ⅱ 2つの評価コロナ ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード