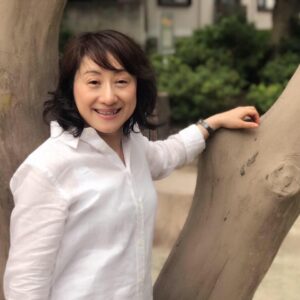≪コロナ政策 中間評価と緊急提言≫死亡者数、増大ペース顕著に
2021年3月5日
---連載⑧ 急増するコロナ死亡と高齢者施設---新型コロナウイルス(COVID19、以下、コロナと表記する)が日本に上陸してからほぼ1年、この間、日本では、死亡者 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード