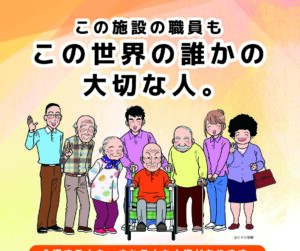介護保険施設の事故防止体制強化 10月1日より本格義務化へ/安全な介護 山田滋氏
2021年11月15日
皆さまもご存知の通り、本年4月の制度改正で介護保険施設の事故防止体制が強化され、10月1日より本格的に義務化されました。今後は取り組みが未実施の場合減算のペナルティが課されます。そ ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード