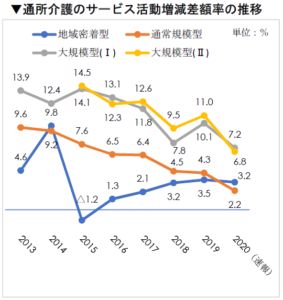特養の医療アクセスに課題/医療法人社団 悠翔会 佐々木淳氏【連載第32回】
2022年6月7日
4月28日に厚労省から発表された調査報告によれば、新型コロナ感染症に対し、施設内での治療体制確保ができた高齢者施設は全国で65%にとどまること、医療リソースの豊富なはずの東京でも、わずか34%にとどま ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード