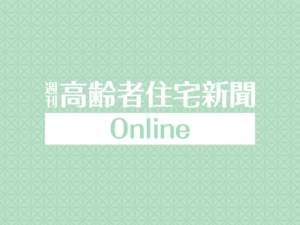共生型デイ、働ける場に 8月、複合施設開設 社会福祉法人きしろ社会事業会
2022年12月23日
社会福祉法人きしろ社会事業会(神奈川県鎌倉市)は、同市で在宅系サービスや施設系サービス、地域包括支援センターなど6拠点を展開。デイサービス、ショートステイの共生型への転換や、地域交流の拠点となる複合施 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。