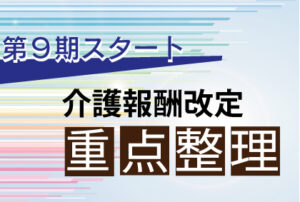誰でも一定水準に達する仕組み ICT人材の育成(前半)【つなぐ支えるICT】
2023年4月22日
山梨県立大学人間福祉学部・福祉コミュニティ学科の伊藤健次准教授は、学生教育の傍ら、福祉専門職の卒後教育にも携わる。特に力を入れてきたのは年間70ケース以上実施する事例を用いたグループスーパービジョンと ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。