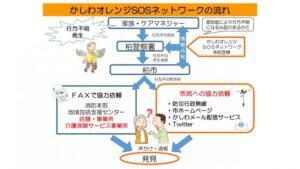正しく理解したい認知症 神奈川歯科大学歯学部 臨床先端医学系認知症医科学分野教授 眞鍋雄太先生【前編】
2023年5月27日
2025年には人口の4人に1人が75歳以上になるという超高齢社会のニッポン。かつて「痴呆症」と呼ばれた認知症への理解も広がってきた…かと思いきや、なかなかそうでもないらしい。これまで約2000人の罹患 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。