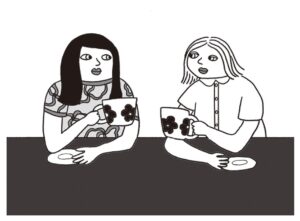みんなの会議/公益財団法人共用品推進機構 星川安之氏
2023年9月17日
面白いとき、一緒に笑える会議 「会議」には、家族・学校・会社・国会・国際など、さまざまな種類がある。広辞苑では「何かを決めるために集まって評議すること」との ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード