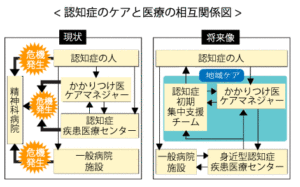「支援」や「サポート」 本人がしたいことを手助けする/女優・介護士・看護師 北原佐和子氏
2023年9月16日
ヘルパー2級の資格取得後、認知症専門施設で勤務を始めたのが2004年。この夏で丸17年間、認知症に対応してきたことにある。 その間、当たり前のように、認知症の方への支援また ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード