【書評】最期まで家で笑って生きたいあなたへ/評:浅川澄一氏
2023年9月18日
小笠原文雄著小学館1,540円(税込)入院にない「笑い」がある自宅死 日本人の70%近くは病院で亡くなる。82%にも達し ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード







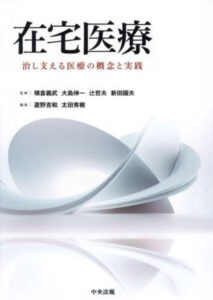
.png)

