2025年7月2日号 4面 掲載
【介護経営者カンファレンスセミナーレポート】現・元記者がホスピス型住宅を考察 訪問看護報酬制度の穴と倫理

高齢者住宅新聞社は6月20日、「第1回介護経営者カンファレンス」を開催。介護事業者、経営層らが多数来場した。当日は、3会場で計13のセミナー・シンポジウムを行った。今号より複数回にわたり、セミナーレポートを掲載する。
終末期支える視点 仕組みに反映を
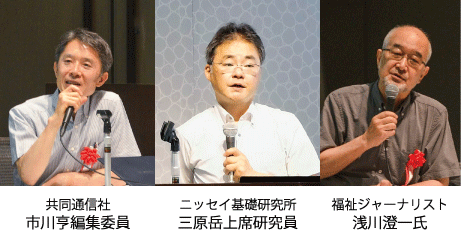
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を活用したいわゆる「ホスピス型住宅」の急増が、訪問看護報酬における不正・過剰請求の問題を浮き彫りにしている。末期がんや神経難病など「別表7・8」に該当する患者を対象とした訪問看護では、1日3回の訪問や複数名体制、深夜・早朝の加算取得が可能となり、報酬が高額化する仕組み。医療保険は介護保険と異なり区分支給限度額が設けられておらず、生活保護や高額療養費制度によって利用者負担も小さいため、事業者側に過剰請求の動機を生みやすい。
不正請求の手法は多岐にわたる。共同通信社の市川亨氏は、一部企業の内部において「睡眠センサーで確認しただけでも訪問と見なす」「患者1人あたり月90万円の売上を目指せ」といったマニュアルが存在していたことを明らかにし、サービスの形骸化を批判した。看護師1人の訪問を2人と偽装、実施していない訪問を記録するなどの虚偽報告が横行し、内部告発者への圧力も強く、退職に追い込まれる事例も後を絶たないという。
訪問看護は本来、訪問診療医が発行する指示書に基づき提供されるが、実態は形式的な手続きにとどまる場合が多い。ファシリテーターを務めた三原岳氏は、医師が現場の実情を把握せず指示書を発行している現状を「制度の空白地帯」と指摘。浅川澄一氏は「医学的判断と言い切れば誰も介入できなくなる構造が問題だ」と言及。まっとうな医師であれば看護師と意見交換を行うが、不正を狙う業者はこの「緩さ」を利用し、医師の関与を形式化することで請求額を最大化しているとした。
報酬制度の見直しとして「包括払い」の導入も議論されているが、三原氏と市川氏の両氏は「過剰請求は抑制できるものの、必要なサービスが削減される懸念がある」と指摘。一方で浅川氏は、症状ごとに標準的報酬を設定するDPC制度のような仕組みへの移行が求められると述べた。
-2.jpg)
シンポジウムの様子
制度設計そのものにも構造的な問題がある。「日本の介護保険制度は『自立支援』を前提に設計されており、『看取り』が想定されていないことに根本的な課題がある」と浅川氏。その結果としてホスピス型住宅への依存が進み、地域包括ケアの理念との乖離を生んでいると睨む。
良質な事業者を見極める視点としては、地域との物理的・心理的な繋がりが重視される。市川氏は「外から見える印象だけでなく、実際に地域との接点をどれだけ持っているかが重要」とした。
ケアの質を考える上で、真に問われるべきは「本人の納得と満足」である。三原氏は「制度の隙間を突くのではなく、現場の声を制度に反映させることが重要だ」と、制度と倫理が両立する持続可能な仕組みづくりの必要性を訴えた。











