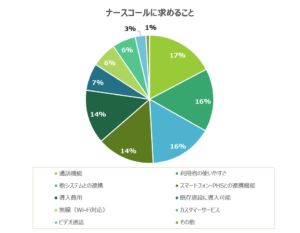「看宗医福」活動推進を 傾聴カフェが多職種連携の場
2023年4月1日
“臨床宗教師”の存在が重要アウェイで活動 布教はせず介護・医療・福祉職などからなる地域住民のための多職種連携ネットワークの中に、僧侶や牧師といった宗教者が加わる「看宗医福」の活動に関する講演会が、 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード