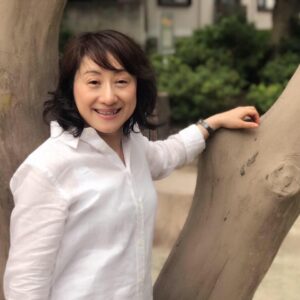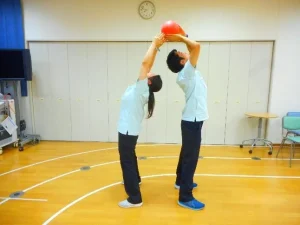【中国養老市場の今】本格的な高齢化へ多士済々 開発バブル後、“特化型”施設流行
2023年5月3日
2010年代以降、中国養老市場において数多くの日系企業が参入を果たす一方、撤退を余儀なくされた会社も少なくない。高齢化が進む人口14億人超の大国が、日系企業にとって依然として魅力的なマーケットであるこ ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード