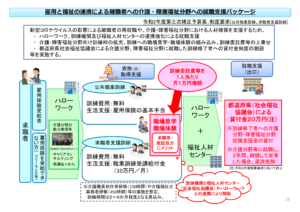生産性向上 実証結果受け「さらなる検証」求む声 介護給付費分科会
2023年5月23日
厚生労働省は4月27日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催。2022年度実証事業「介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業」の結果を報告した。テクノロジー及び介護助手の活用については ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。