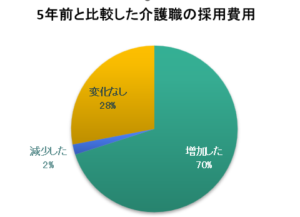【職員確保へのイシュー➂】「依存」から脱却に向け慎重な採用活動を
2023年8月25日
ハローワーク機能強化 福祉人材センターも民間の紹介事業者の課題が指摘されるとともに、機能強化を期待されているのがハローワークだ。「人材確保対策コーナー」の拡充や各ハローワークの職種 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能
有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。